Amazon販売において、「商品は売れているはずなのに、なぜか手元にお金が残らない」といった経験はありませんか。Amazonの手数料体系は非常に複雑で、販売手数料、FBA配送代行手数料、在庫保管手数料、さらには返品コストや広告費など、多岐にわたるコストが発生します。
これらを感覚だけで把握しようとすると、気付かないうちに「売れば売るほど赤字になる商品」を取り扱ってしまうリスクがあります。
「1個売れたら、正確にいくら儲かるのか」をSKU(商品)ごとに可視化できれば、自信を持って仕入れを行い、利益の出る価格設定が可能になります。それを実現するのが「費用計算シート」です。
この記事では、エクセルやGoogleスプレッドシートを使って、誰でも簡単に作れる「利益管理の仕組み」を解説します。初心者の方でも迷わず実践できるよう、必要な情報の集め方から、計算式の組み方、そして算出された数字をどう判断して改善につなげるかまで、ステップバイステップで紐解いていきます。
準備:正確な計算のための「情報集め」

正確な利益計算には「正しいデータ」が不可欠です。計算シートに入力する前に、まずは以下の情報を手元に揃えましょう。ここの精度が、最終的な利益計算の精度を決めます。
SKUごとに集めるべき5つの必須データ
まずは1つの商品(SKU)を例にして、以下の情報をメモ帳などに書き出してください。
1. 商品の基本情報(ASIN・SKU・商品名)
どの商品を計算しているのか迷わないよう、管理番号を控えます。特にバリエーション(色・サイズ違い)がある場合は、それぞれ手数料が異なる可能性があるため、個別に管理する必要があります。
2. 販売予定価格(税込・税抜の統一)
Amazonで販売する予定の価格です。ライバルセラーの価格や、市場の相場を参考に設定します。計算シート内では、消費税の扱い(内税か外税か)を統一することが重要です。
3. 仕入れ原価(1個あたり)
商品そのものの代金です。セット商品の場合は、セットを組むために必要な個数分の合計金額を算出します。
4. 梱包後のサイズと重量(実測値)
ここが最も重要なポイントです。AmazonのFBA手数料は、商品のサイズではなく「梱包後のサイズと重量」で決まります。
商品本体のサイズではなく、OPP袋や化粧箱に入れ、ラベルを貼り、Amazonの倉庫に納品する「最終形態」でメジャーを使って測ってください。数ミリの誤差で手数料区分が変わり、利益が数百円変わることも珍しくありません。
5. その他の経費(見えないコスト)
ここを見落とすと計算が狂います。以下のような細かい費用も1個あたりに換算して洗い出しましょう。
- 納品送料:自社(または海外工場)からAmazon倉庫へ送るための送料。ダンボール1箱の送料を、中に入っている商品数で割って算出します。
- 関税・消費税:輸入商品の場合は必須です。
- 資材費:商品を入れる袋、サンクスカード、商品ラベル代など。
- 作業費:検品や梱包を外注している場合の単価。自社で行う場合も、時給換算してコストに含めるのが理想です。
利益の「合格ライン」を決めておく
計算を始める前に、自社の「利益目標」を明確にしておきます。「いくら儲かればOKとするか」の基準がないと、計算結果を見ても良し悪しが判断できないからです。
一般的な物販ビジネス(特に輸入やせどり)の場合、一つの目安として「営業利益率 20%」を目指すと安全圏と言われています。
(例:1,000円で売るなら、全ての手数料を引いて200円手元に残る状態)
もちろん、回転率(売れるスピード)が非常に速い商品なら10〜15%でも許容できるかもしれませんし、逆にリスクが高い商品なら30%以上欲しいかもしれません。自分なりの「合格ライン」を持っておくことが、ぶれない判断につながります。
計算シートの作成:エクセルで仕組みを作る

データが揃ったら、実際に計算シートを作っていきます。複雑な関数は必要ありません。四則演算(+−×÷)ができれば十分です。一度作ってしまえば、あとは数値を入れ替えるだけで何度でも使えます。
シートに入力する項目と構成案
スプレッドシートの1行目に、以下の項目を左から順に見出しとして入力します。
| 分類 | 項目名 | 入力内容の例 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 商品名 / ASIN | iPhoneケース 黒 |
| 収入 | 販売価格 | 2,000円 |
| 原価 | 仕入れ単価 | 500円 |
| Amazonコスト
(FBAシミュレーターで確認) | 販売手数料 | 200円 (10%) |
| 配送代行手数料 | 434円 | |
| 在庫保管手数料 | 10円 (月額換算) | |
| 自社経費 | その他経費合計 | 100円 (送料+梱包材) |
| 結果
(自動計算) | 利益額 | 756円 |
| 利益率 | 37.8% |
自動計算の数式を入れる
手計算によるミスを防ぐため、結果の欄には数式を入れておきましょう。
- 利益額 = 販売価格 - (仕入れ単価 + 販売手数料 + 配送代行手数料 + 在庫保管手数料 + その他経費)
- 利益率 = 利益額 ÷ 販売価格(※セルの書式を%表示にする)
こうすることで、例えば「販売価格を1,800円に下げたらどうなるか?」「仕入れ値を50円安くできたらどうなるか?」といったシミュレーションが瞬時にできるようになります。
難関「Amazon手数料」の正確な調べ方
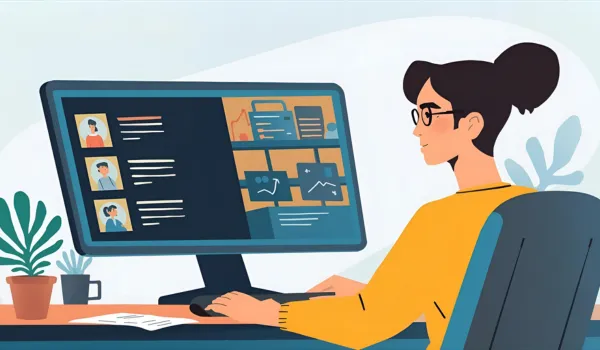
これはカテゴリやサイズによって複雑に変動するため、手計算で出すのは危険です。必ずAmazon公式のツールを使って正確な数値を出してください。
「FBA料金シミュレーター」を使いこなす
Amazonには、手数料を自動計算してくれる無料ツール「FBA料金シミュレーター」があります。Googleで検索すればすぐに見つかります。
- 商品検索:売りたい商品、またはサイズやカテゴリが似ている既存の商品のASINを入力して検索します。
- 数値入力:「販売価格」「配送料(自社からFBA倉庫まで)」「商品原価」を入力します。
- 計算実行:ボタンを押すと、Amazonの各種手数料が自動で計算され、純利益が表示されます。
ここで表示された「販売手数料」「配送代行手数料」などの数値を、先ほどの自作シートに転記します。
「サイズ区分」の落とし穴に注意
FBAの配送代行手数料は、「サイズ区分(標準サイズ、大型サイズなど)」によって料金が階段状に変わります。
例えば、梱包サイズが「厚さ3.3cm」を超えると、メール便サイズ(小型)から標準サイズ扱いになり、手数料が数百円上がってしまうことがあります。
シミュレーションをする際は、「あと数ミリ小さく梱包できれば、ワンランク安い手数料区分に入らないか?」という視点を持つことが、利益率アップの秘訣です。
見落としがちな「長期在庫保管手数料」
通常の在庫保管手数料とは別に、在庫が長期間(1年以上など)売れ残ると、高額な「長期在庫保管手数料」が加算されます。
計算シートには、商品がスムーズに売れた場合の「標準パターン」だけでなく、売れ残った場合の「悲観パターン」も想定しておくと、よりリスクに強い経営ができます。
計算結果の分析と「次の一手」

算出された利益率を見て、出品するかどうか、どう改善するかを判断します。
パターン別の対処法
ケースA:利益率が目標(例:20%)を超えている
素晴らしいです!すぐに仕入れと出品の準備を進めましょう。
ただし、油断は禁物です。ライバルが値下げをしてくる可能性も考慮し、「価格を10%下げてもまだ黒字か?」を確認しておくと盤石です。
ケースB:利益は出るが、目標に届かない(例:10%程度)
このまま出品するのはリスクが高いです。広告費をかけたり、少し値下げ競争が起きたりすると、すぐに赤字転落してしまいます。以下の改善策を検討してください。
- 仕入れ交渉:「一度に〇〇個買うから、単価を下げてほしい」と交渉する。
- セット販売:2個セット、3個セットにして客単価を上げ、1個あたりの配送手数料や送料の比率を下げる。
- サイズ圧縮:パッケージを薄くして、FBA手数料の区分を下げる。
ケースC:利益がほとんどない、または赤字
残念ながら、この商品は今のままでは扱えません。「仕入れを見送る」というのも立派な経営判断です。
無理に販売して赤字を垂れ流すより、その資金を別の儲かる商品の仕入れに回しましょう。
広告費の予算を組み込む(損益分岐点の把握)
Amazon販売では、広告(スポンサープロダクト広告など)を使うことが一般的です。
計算シートで出た「1個あたりの利益額」が、そのまま「広告費として使える上限額(損益分岐点)」になります。
例えば、1個あたりの利益が500円なら、1個売るために広告費を500円かけてしまうと利益はゼロになります。
「利益の30%までなら広告費に使っていい」といったルールを決め、手元に残る最終利益(営業利益)までシミュレーションしておくと安心です。
まとめ
今回ご紹介した手順で「費用計算シート」を作り、商品を1つずつ検証してみてください。
- 材料を揃える:原価、サイズ、送料などの数字を正確に集める。
- ツールを使う:FBA料金シミュレーターで手数料を正確に出す。
- シートに入力する:自動計算で「利益額」と「利益率」を出す。
- 判断する:目標利益に届かないなら、改善するか、撤退する。
この数分の手間を惜しまないことが、あなたのビジネスから「理由のわからない赤字」をなくし、確実に利益を積み上げるための最短ルートです。
まずは今日、主力商品のデータを使って、一度計算してみることから始めてみましょう。
<ご注意>本記事の内容は、執筆時点の情報に基づいています。Amazonの手数料体系やFBAのルールは頻繁に変更されるため、必ず公式サイトやAmazonセラーセントラルで最新情報を確認した上で、最終的な判断を行ってください。
