Amazonの売上データを見て「今月の売上は去年と比べてどう変わったか」をすぐに知りたい。
そんなときはAmazon QuickSightでの前年比表示が便利です。
ECビジネス、特にAmazon販売において「前年同月比(YoY)」は、ビジネスの健康状態を測るための最も重要な体温計です。単月で売上が上がった下がったと一喜一憂するのではなく、季節性(シーズナリティ)を考慮した上で「昨年の同じ時期より成長しているか?」を確認しなければ、正しい経営判断は下せません。
しかし、いざ可視化しようとすると「どの数字を使えばいいの?」「日付はどう処理するの?」「Excelだとデータが重すぎて開かない」といった壁にぶつかりがちです。
この記事では、初心者の方でも迷わないように、データの準備からQuickSightでの計算式の作成、そして意思決定に直結する見やすいグラフの作り方までを、やさしく順を追って解説します。
まずは基本を押さえて、Amazon売上の「昨年との違い」をパッと把握できるダッシュボードを作り上げましょう。
1. データの準備

データ分析も「土台づくり(データ整形)」が成功の8割を握っています。
ここで決めておくべきなのは、「売上として使う数字(NetSales)」と「月ごとの集計に使う日付」の2つ。ここがブレると、あとで計算結果を見たときに「セラーセントラルの数字と合わない!」という混乱を招きます。
「売上」として使う数字を決める(NetSalesの定義)
「売上(NetSales)」に何を含めるか、チーム内でルールを決めましょう。
Amazonからダウンロードできるレポートには、多種多様な金額データが含まれています。一般的には以下のように整理して計算します。
| 項目 | 扱い方の例と理由 |
|---|---|
| 商品代金 | プラス(売上の基本) これがベースとなります。 |
| 配送料 | プラス(または除外)自社出荷で送料を取っている場合は売上に含めますが、分析のノイズになるため除外するケースもあります。 |
| 割引・プロモーション | マイナス(差し引く)クーポンやタイムセール値引きです。これを引かないと「見かけの売上」は高いのに利益がない状態になります。 |
| 返品・キャンセル | マイナス(差し引く)データによってはプラスの値で入っていることがあるため、必ずマイナスとして計算します。 |
| Amazon手数料 | 引かない(ことが一般的)「売上推移」を見る目的であれば、手数料を引く前の金額(流通総額)で見るのが一般的です。粗利を見たい場合は引きます。 |
これらを足し引きして、数字(NetSales)を1つ定義します。
集計する「日付」を決める(タイミングの統一)
「いつの売上とするか」の基準となる日付も重要です。
Amazonには複数の「日付」が存在します。目的によって使い分けましょう。
- 注文日(Order Date):お客様が「購入した」瞬間です。マーケティングの効果や、季節ごとの需要トレンド(「今どれくらい人気か」)を知りたい時におすすめ。通常はこれを基準にします。
- 出荷日(Shipment Date):商品が倉庫から発送された日です。売上が確定するタイミングなので、会計上の売上計上や物流の動きを見たい時に使います。
- 入金日(Payment Date):Amazonから入金が確定した日です。キャッシュフローを見たい時に使いますが、販売分析には向きません。
QuickSightで使う時は、この日付データが「日付型(Date)」になっている必要があります。もしCSVの段階で「2023/10/01」のような文字データになっている場合は、QuickSightのデータセット編集画面でparseDate関数を使って日付型に変換しておきましょう。
データがない月はどうする?
売上がなかった月の扱いも決めておきましょう。
ここが意外な落とし穴です。「売上が0円だった月」と「まだデータが存在しない未来の月」を区別しないと、グラフがおかしくなります。
- 過去の月でデータがない:「売上0円」として扱います。そうしないと、折れ線グラフが勝手に前月と翌月をつないでしまい、「売上がなかった事実」が見えなくなってしまいます。
- 未来の月:除外します。0円として含めてしまうと、前年比が「-100%(大暴落)」のように表示されてしまいます。
QuickSightで「前年比」を計算

データが整ったら、いよいよ計算です。
Excelで前年比を出そうとすると、VLOOKUP関数を駆使したり、ピボットテーブルを触る必要がありますが、QuickSightには便利な専用機能があるので、それを使えば難しくありません。
便利な関数「periodOverPeriod」を使う
QuickSightには、「前の期間と比べる」ための専用の計算式(関数)があります。これを使えば、「今年の売上」と「去年の売上」の差や比率を簡単に計算できます。
【やりたいこと】
昨年の同じ月と比べて、何パーセント成長したかを知りたい。
【計算式のイメージ】( 今年の売上 - 去年の売上 ) ÷ 去年の売上
【QuickSightでの記述例】
計算フィールドを作成し、以下の関数を使用します。
periodOverPeriodPercentDifference(sum({NetSales}), {OrderDate}, YEAR, 1)この数式は、以下の意味を持っています。
「売上の合計(sum NetSales)を、注文日(OrderDate)を基準にして、1年前(YEAR, 1)と比較して、%の差(PercentDifference)を出してね」
これを設定するだけで、グラフ上の年月を自動で判別し、その1年前の数字と比較した結果を算出してくれます。
「見やすいグラフ」を作る

計算ができたら、見やすい画面(ダッシュボード)に仕上げましょう。
ただ数字を並べるのではなく、「パッと見て、良いか悪いか判断できる」ことが重要です。
「結論」を先に見せる
画面の一番上には、細かいグラフではなく「結論」を置きます。
「KPI(重要業績評価指標)ビジュアル」を使い、「今月の売上着地見込み」と「対前年比(何%アップしたか)」を大きな文字で表示します。
【テクニック:条件付き書式】
前年比が100%を超えていれば文字を緑色に、割れていれば赤色に自動で変わるように設定します。これだけで、マネージャーや経営陣は「今月は順調だな」「お、何かトラブルか?」と一瞬で状況を把握できます。
コンボチャートで「傾向」をつかむ
月ごとの推移を見るには、「コンボチャート(棒グラフと折れ線グラフの組み合わせ)」が最適です。
- 棒グラフ(売上金額):「売上の規模」を表します。どの月が繁忙期なのか、ボリューム感が分かります。
- 折れ線グラフ(前年比または前年売上):「成長の勢い」を表します。棒グラフ(売上)が高くても、折れ線(成長率)が下がっていれば、ビジネスの勢いが落ちているサインです。
このように、「量(棒)」と「質(線)」を重ねて見ることで、数字の裏にあるストーリーが見えてきます。
フィルターで「深掘り」できるようにする
画面の上部には、「期間」や「商品カテゴリ」「ブランド名」を選べるフィルター(コントロール)を設置します。
フィルターで特定のブランドに絞り込み、「どの商品が足を引っ張っているのか」をドリルダウンして犯人探しができるようにしておきます。
数字が合っているか確認(検証と運用)
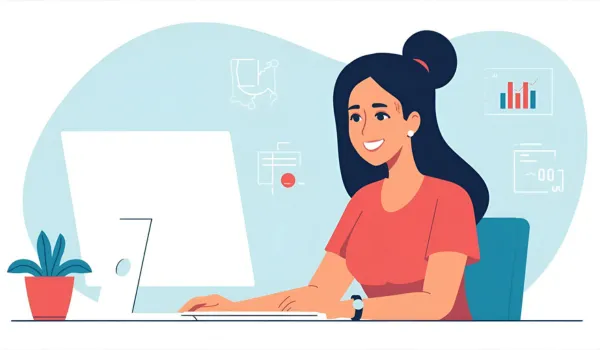
ダッシュボードができたら完成ではありません。「この数字、本当に合ってるの?」という疑いを晴らす作業が必要です。一度でも間違った数字を見せてしまうと、ダッシュボードの信頼性は失われ、誰も見てくれなくなります。
毎月の「答え合わせ」をルーティンにする
月に一度は、元のデータ(Amazonセラーセントラルのビジネスレポートなど)と、QuickSightの数値を突き合わせる検算を行ってください。
- 合計値の確認:「今月の売上合計」が、セラーセントラルの数字と一致しているか?
- ズレの原因調査:もしズレていたら、返品のタイミングや、キャンセルの扱い、保留中注文の計算などが合っているか確認します。
- 異常値のメモ:数字が急に増えたり減ったりしている月があれば、その理由(プライムデーがあった、在庫切れで2週間売れなかった、など)をメモしておきます。
来年の同じ時期にデータを見たとき、「なんで去年はこんなに売れてたんだっけ?」と迷わずに済みます。
まとめ
Amazon売上の前年比を見るには、「データの定義(売上と日付)を固める」「QuickSightの計算機能を使う」「見やすいグラフにする」の3ステップが大切です。
Excelで毎月手作業で集計していると、作業すること自体が目的になってしまい、「数字を見て考える時間」がなくなってしまいます。
QuickSightで自動化されたダッシュボードを作れば、朝起きて画面を見るだけで、「昨年より120%成長している!この調子で広告を強めよう」あるいは「昨年割れしている…在庫切れが原因か?」といった「次の一手」をすぐに考えられるようになります。
まずは手元のデータを使って、小さなグラフを一つ作ってみることから始めましょう。過去のデータが、未来の売上を作るための羅針盤になるはずです。
<ご注意>本記事は執筆時点の情報に基づいています。Amazonの仕様やQuickSightの機能は変更される場合がありますので、最新情報は必ずAWS公式ドキュメント等で確認してください。
