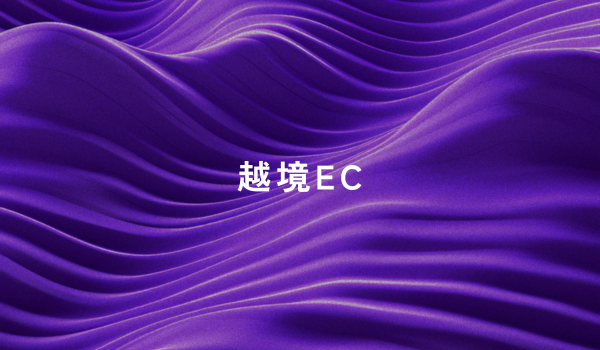海外からの問い合わせは増えているのに「どこから手を付ければいい?」「関税や配送コストが読めず不安」「英語サポートに自信がない」そんな壁にぶつかっていませんか。
本記事では、越境ECの
- 基本概念
- 市場調査
- 物流
- 法規制等の準備
- 立ち上げステップ
- 成功事例
- 失敗しないための注意点
を解説します。
多くの企業がつまずく「関税計算」「多通貨決済」「現地SNS運用」のコツについても解説していくので、越境ECを始めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
越境ECとは?国内ECとの違いを押さえよう

越境ECとは、自社の商品やサービスを海外の消費者に向け、インターネットを通じて販売する仕組みのことです。
日本国内で商品を販売する場合と異なり、購入者の国や言語、税制、配送事情などが大きく変わるため、手続きやコストが複雑化しがちです。
しかし、その分広大な海外市場で新規顧客を獲得できるチャンスがあるのも事実です。
特に訪日観光客が減少している昨今では、直接海外ユーザーを取り込みたいと考える企業が増えています。
越境ECと国内ECの違いを正しく理解し、海外向けならではの課題とメリットを把握しておくことが成功への第一歩です。
越境ECを始める前に確認すべき3つの準備
海外向けECを立ち上げるには、事前の下調べが欠かせません。
ここでは
- 市場リサーチ
- 商品・物流インフラ
- 法規制・税金・関税
の3つに注目して、ポイントを解説します。
どんなに魅力的な商品を用意しても、販売の基盤が整っていないと安定した成果につながりにくいため、入念な準備が重要です。
市場リサーチ:ターゲット国とニーズを把握
はじめに、どの国を主なターゲットにするのか明確にする必要があります。
国や地域によって求められる商品ジャンルや流行、価格帯が大きく違うからです。
例えば、高品質な日本製品に対する信頼度が高い国もあれば、リーズナブルな日用品を大量に購入する文化が根付いている国もあります。
SNSや現地メディアをチェックする、海外向けアンケートを実施するなど、複数の情報源から市場ニーズを探りましょう。
競合商品のレビューを調べるのも、顧客の不満や要望を把握するうえで役立ちます。
こうした情報を総合的に分析し、自社商品の海外展開における優位性と改善点を洗い出しておくと、スムーズに販売戦略を組み立てられます。
商品・物流インフラを整える
次に、物流網や倉庫などのインフラ面を固めることが大切です。
海外配送では配送料や配達日数、追跡サービスの有無など、消費者の満足度を左右する要素が増えます。
下記のように、配送会社や方法を比較検討するときのポイントを押さえておきましょう。
- 対応できる国・地域の範囲
- 配達スピードと送料のバランス
- 商品の追跡機能や補償の有無
例えば、海外専用の国際配送サービスを利用すれば、通関手続きや輸送のトラブル対応をスムーズに行える場合があります。
逆に、自社で梱包や発送を行う場合は業務負荷が増すため、工数や人員配置を事前に考慮しましょう。
物流面のトラブルは顧客体験にも直結するため、信頼できるパートナー企業や合理的なフローを確立しておくことが、安定した越境EC運営の基礎になります。
法規制・税金・関税の基礎知識を押さえる
海外向けECを立ち上げる際には、対象国や地域の法制度を事前にチェックしなければなりません。
食品や化粧品、医薬品などは輸入規制が厳しい場合があり、販売許可が必要なケースも考えられます。
また、越境取引の収益に対して課される税金や関税の制度は国ごとに異なるため、税理士や専門機関に相談しておくと安心です。
輸入時にかかる関税は商品カテゴリにより大きく変わることがあるため、利益率を予測するうえでも正確な情報が欠かせません。
法規制の不備は販売停止につながる恐れもあるので、トラブルを避けるためにもプロのアドバイスを受けておきましょう。
越境ECに必要な費用とスケジュール感を把握しよう

海外向け販売には、日本国内だけで展開する場合よりも費用や準備期間がかかることが多いです。
サイトの多言語対応や国際配送、現地向け広告など新たなコストが発生するため、最初に資金繰りと運用計画をしっかり立てておくことが大切です。
時間とコストをどの程度見込めばいいか把握しておくと、焦りや無理のない越境EC運営が可能になります。
初期投資とランニングコストの内訳
越境ECを導入する際の主な初期投資には、以下のようなものがあります。
サイト構築費用や在庫調達費、翻訳対応費などは忘れがちな項目となるため、あらかじめ予算に入れておきましょう。
- 海外対応サイトの制作・設定費用
- 商品在庫の確保(仕入れコストなど)
- 翻訳や多言語サポート体制の整備費
運用が始まってからも、決済手数料や国際配送コスト、広告出稿費、システム利用料など継続的なコストがかかります。
無計画に出店すると赤字が積み重なる恐れがあるため、「いつまでに黒字化するか」「どれくらいの売上が必要か」を明確にすることが大切です。
売上シミュレーションと損益分岐点
何件売れれば利益が出るのかを把握しておくと、プロモーションにかける費用や目標設定が立てやすくなります。
1商品あたりの平均単価と利益率をもとに、月間販売数を予想して損益分岐点を計算してみましょう。
もし想定よりも広告費が高騰したり、関税が想定より大きくなった場合は、価格設定や販売国の再検討が必要になるかもしれません。
こうした売上シミュレーションを定期的に行うことで、柔軟に戦略を修正しやすくなります。
活用できる補助金・支援制度のチェックリスト
政府や自治体、JETROなどの公的機関が海外展開向けに補助金や支援事業を用意していることがあります。
例えば、海外プロモーション費用の一部を助成してくれるケースや、展示会出展をサポートしてくれる制度などが代表的です。
自社のビジネスモデルに合った補助金を活用できれば、初期投資や広告費を削減し、リスクを抑えながらチャレンジしやすくなります。
申請には期限や細かな条件があるため、早めに情報収集をしておくと良いでしょう。
越境ECの始め方ステップガイド

ここからは、海外市場へ実際に展開するための手順を具体的に見ていきます。
販売チャネルの選び方や決済・配送手段の整備、マーケティング施策など、順を追って進めることで
「越境ECをどう始めるか」がイメージしやすくなるでしょう。
ぜひ、自社の事情に合わせてカスタマイズしながら進行してください。
ステップ1:販売チャネルを選択する
越境ECをスタートするにあたり、まずは「自社サイトで展開するか、それとも既存の海外ECモールに出店するか」を決定します。
自社サイトならブランディングや顧客情報の管理がしやすい反面、プロモーションに力を入れないと集客に苦労するかもしれません。
一方、海外ECモールはすでに豊富なユーザーを抱えていますが、モール規約や手数料の制約があることを踏まえておきましょう。
自社サイト構築(Shopify・ebisumart など)
自社サイトで海外販売に取り組む場合は、多言語対応や多通貨決済機能など越境対応に必要な機能を備えたプラットフォームを検討するのが一般的です。
Shopifyは世界中に利用者が多く、アプリで機能拡張しやすいのがメリットです。
ebisumartは国内事例も豊富で、柔軟なカスタマイズ性が魅力です。
ただし、カスタマイズや運用にかけられる社内リソースや予算次第では、開発外注やプラグインの利用が不可欠な場合もあります。
しっかりと要件定義を行ったうえで、最適なサービスを選ぶとよいでしょう。
モール出店(eBay・Amazon Global など)
海外のECモールで特に有名なサービスとしてはeBayやAmazon Globalなどが挙げられます。
すでに膨大なユーザー基盤があるため、集客を一から構築する必要がやや軽減されるのはメリットです。
その反面、モール独自の手数料や出品ルールがあるので、コストや運営方針が合わなければ思ったほど利益が残らない可能性もあります。
商品数が多い場合は、モール内での検索対策やレビュー管理も重要になってくるため、社内で対応できるかどうかの見極めが必要です。
ステップ2:決済・配送・カスタマーサポートを設計
販売チャネルが決まったら、ユーザーが不安なく購入できる仕組みを整えましょう。
決済方法は、クレジットカードやPayPalなどの一般的な手段だけでなく、ターゲット地域で主流の電子決済や銀行振込に対応するとより安心感を与えられます。
配送では配送会社を複数社検討し、速達や追跡付きなどの選択肢を用意するのが望ましいです。
また、問い合わせやクレーム処理に対応するカスタマーサポート体制も欠かせません。
多言語対応のスタッフを配置するか、翻訳ツールを効果的に使うなど、ユーザーが困ったときに迅速に連絡できる環境を作るとリピーター獲得につながります。
ステップ3:マーケティング施策で認知を拡大
いくら使いやすいサイトやモールを用意しても、ターゲット層に見つけてもらわなければ売上にはつながりません。
そこで、SNS広告や海外検索エンジンへの最適化、現地インフルエンサーとの連携など、多角的な施策が必要になります。
特に現地語や文化に寄り添った広告表現は効果的ですが、ネイティブチェックを怠ると誤訳や失礼な表現になりかねません。
しっかりと現地のトレンドや言語事情を調査しながら、適切なプロモーションを展開することが成功の秘訣です。
運用体制とツール選定のベストプラクティス

海外への販売を安定的に続けるには、運用担当者の負荷を適切に管理し、必要なツールをうまく組み合わせることが大切です。
すべてを内製化すると工数が膨らみ、肝心の戦略立案や商品開発に時間を割けないケースもあります。
そこで、社内リソースをどこに集中させるかを明確にし、足りない部分は外部の知見やサービスを活用する方法がおすすめです。
社内リソースとアウトソーシングの最適バランス
海外展開には言語や法規制など、国内ECとは異なる知識が求められます。
社内にそれらの専門スキルが少ない場合は、翻訳会社やコールセンター、広告代理店などと連携し、負荷を外部に振り分けるのが合理的です。
一方、自社の特徴やブランドイメージを深く理解しているのは社員であるため、重要な戦略決定や商品開発は社内で行うほうがスピーディなケースも多いです。
外部パートナーと社内の役割分担を明確にし、無理なく長期的に運営できる体制を整えましょう。
多通貨決済・翻訳・在庫管理ツールの比較
円だけでなく、ドルやユーロ、ターゲット国の通貨で決済できれば、ユーザーにとって購入ハードルが下がります。
翻訳ツールも、製品名や商品説明を多言語化する場合に役立ちますが、文化的なニュアンスまで完全に反映できるわけではありません。
そのため、重要なページはネイティブチェックを入れるなどの工夫が必要です。
また、在庫管理ツールを導入することで、国・倉庫ごとの在庫把握や出荷指示を自動化できれば、誤出荷や在庫切れといったミスを減らしやすくなります。
ツール導入費用と利便性を比較しながら、最適な組み合わせを検討してください。
KPI設定とデータ分析でPDCAを回す方法
海外向けECをスタートした後は、「月間売上」「カート放棄率」「顧客単価」など、複数のKPIを設定すると課題の原因を発見しやすくなります。
データをもとにマーケティング施策を微調整し、成果を検証して次の改善策を練るというPDCAサイクルを意識的に回しましょう。
例えば、広告費に対してCVR(購入率)が悪い場合は、クリエイティブの見直しやターゲティングの再設定が必要かもしれません。
数字で結果を確認しながら、小さく試行錯誤を繰り返すことが、最終的な売上拡大につながります。
成功事例に学ぶ越境ECの勝ちパターン

実際に海外展開で成果を上げている企業のケースを参考にすると、自社に置き換えて具体的な施策を思い描きやすくなります。
ここでは、ニッチな商品分野に特化した売り方や、現地SNSを活用したアプローチなど、代表的な成功パターンを取り上げます。
ニッチ商品のグローバル展開
海外ではレアな日本特有の商品が、思わぬ人気を集めることがあります。
例えば、職人が作る和雑貨や漫画・アニメ関連の商品、限定コスメなどは高い注目を浴びやすいジャンルです。
ある事例では、日本の伝統工芸品を動画と写真でわかりやすく紹介することで現地ファンが増え、その口コミ効果によりブランド認知度が急上昇しました。
ニッチ分野であっても強みが明確であれば、グローバルに支持される可能性が十分あります。
現地SNSを活用したファンコミュニティ形成
海外向けに販売するなら、ターゲット国で主要なSNSをチェックし、積極的に活用してみるのも一つの手です。InstagramやYouTubeだけでなく、地域によっては独自のSNSが普及しているケースもあります。
美容やファッションなど、ビジュアルに訴求力のある分野ではインフルエンサーやクリエイターとのコラボレーションが有効です。
投稿を通じて商品を紹介し、気に入ったユーザーが自発的にシェアしてくれれば、短期間で顧客層が拡大する可能性も高まります。
こうしたファンコミュニティを形成すると、リピーターやロイヤル顧客を育てやすくなるでしょう。
越境ECで失敗しないための注意点
越境ECは多くの企業に新たな販路をもたらしますが、国内取引と比べるとリスクや対応コストが大きいのも事実です。
ここでは、よくある失敗パターンを事前に回避するための注意点をまとめています。
しっかり備えておけば、大きなトラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。
言語・文化の差による誤解を防ぐポイント
海外ユーザーがよく感じる不満として、商品説明やヘルプページが現地言語でしっかり翻訳されていない、または文化背景が反映されていないことが挙げられます。
誤訳だけでなく、日本独自の文言やイメージが海外では通じないケースもあるため、ローカライズを意識した表現が必要です。
特に、使用方法や成分表示が重要な商品は、誤解を招くとクレームや返品につながる恐れがあるので注意しましょう。
現地スタッフやネイティブの翻訳者による最終チェックを行うことで、文化的背景の差を最小限に抑えることができます。
物流遅延・返品リスクへの備え
国際配送は国内配送よりも時間や手続きがかかるため、遅延が起こるリスクが高まります。
発送後も定期的に配送状況を確認し、配送トラブルが発生した場合は素早いリカバリー対応を行いましょう。
返品ポリシーも明確にしておき、商品到着時の破損や不良品に対して、代替品や返金をどのように進めるかを決めておくことが大切です。
ユーザーが安心して購入できる環境づくりは、信頼獲得とリピーター育成につながります。
為替変動とコスト計算の落とし穴
為替レートは日々変動するため、レートが大きく動いたときに利益率が想定より下がってしまう場合があります。
特に大量取引を行うショップでは、為替リスクを管理する体制を整えておきましょう。
レートが有利な時期にまとめて商品を仕入れる、価格設定を随時調整するなどの対策が考えられます。
また、国際配送や税関費用などの細かいコストを見落としていると、実際にはあまり利益が残らない結果になりかねないため、定期的にコスト試算を行う習慣をつけてください。
まとめ

海外市場を開拓する際は、ターゲット国のニーズ調査や物流・法規制への対応など、国内ECに比べて一段階多い準備が求められます。
翻訳やマーケティング手段の最適化、運用体制の整備などを進めながら、実際の販売データを検証して改善を重ねることが重要です。
この記事で紹介したステップや事例、注意点を参考に、自社に合わせた計画を練りつつ着実に海外販売をスタートしてみてください。
うまく軌道に乗せられれば、国内だけでは得られない大きなビジネスチャンスをつかむ可能性があります。